超回復理論とは?
筋トレや激しい運動をしたあと、筋肉は疲れてダメージを受けます。
このダメージを修復する過程で、体は前よりも少し強くなろうとします。これが「超回復(ちょうかいふく)」です。
イメージでいうと…
筋トレで筋肉にダメージを与える(筋肉が一時的に弱くなる)
回復中に筋肉が修復される(元に戻る)
元に戻るだけじゃなく、「次に備えてもっと強くなろう!」と、少しだけ強くなる(これが超回復)
超回復が起こるタイミング
トレーニング後 24〜72時間(種目や強度によって異なる)
このタイミングで次のトレーニングをすると、効率よく成長できる!
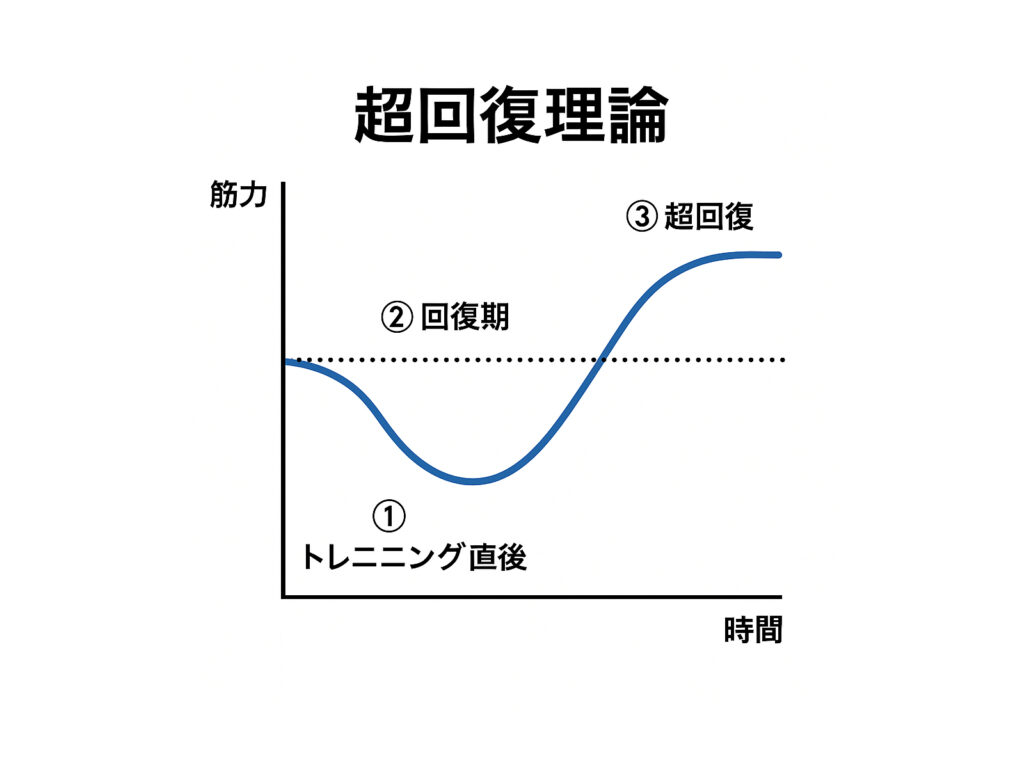
💥 超回復理論のメリット
効率的な成長:正しいタイミングで鍛えることで、無駄なく強くなれる
ケガの予防:休養をしっかり取ることで、疲労がたまりにくい
トレーニングの計画が立てやすい:何曜日に何を鍛えるかを組みやすい
超回復理論にはこんな疑問や欠点もある
① 全部の筋肉が同じスピードで回復するわけじゃない
筋肉の種類、大きさ、個人の体質によって回復スピードはバラバラ
例えば、脚の筋肉(大筋群)は回復に時間がかかり、腕の筋肉(小筋群)は早めに回復することがある
② 生活習慣に左右されやすい
睡眠不足、栄養不足、ストレスがあると回復が遅くなる
逆に、しっかり食べて寝ていれば早く回復することも
③ 超回復のタイミングは目に見えない
「今がちょうどいいタイミングだ!」ってのは実感しにくい
④ 高度なアスリートには当てはまらないこともある
トップレベルの選手は、毎日同じ部位を鍛えても成長することがある(食事・睡眠・ケアが完璧なため)
このように超回復理論はいくつかの疑問点や欠点がみられます。
ではフィットネス疲労理論とはどういった理論なのか?
💡 フィットネス疲労理論とは?
フィットネス疲労理論は、トレーニングの効果(パフォーマンス)が、「フィットネス(体力)」と「疲労(疲れ)」という2つの相反する要素のバランスによって決まる、という考え方です。
🏋️ トレーニングが与える「2つの効果」
フィットネス効果(+)
→ 筋力や持久力が向上するプラスの影響
→ 長期的に持続する(数日〜数週間)
疲労効果(−)
→ トレーニングによる一時的な疲労やダメージ
→ 短期的に強く現れ、数時間〜数日で回復
ポイントとなる考え方
フィットネス トレーニングで得られる正の効果(筋力アップなど)
疲労 トレーニングで発生する一時的なマイナス効果(疲れ)
パフォーマンス フィットネスと疲労の差で決まる状態(=結果)
🔽
パフォーマンス = フィットネス − 疲労
✅ フィットネス疲労理論の活用法
トレーニング直後:疲労が大きく、パフォーマンス低下
数日後:疲労が取れてフィットネス効果が残り、ピークに近づく
重要な試合・テスト:疲労が少ない状態で臨むとベストパフォーマンス
🧩 超回復理論との違い
超回復理論 ⇔ フィットネス疲労理論
主に筋肉の回復を重視 ⇔ パフォーマンス全体を重視
シンプルで初心者向け ⇔ より現実的・戦略的な理論
🎯 まとめ
トレーニングは、フィットネスを高めつつ、疲労をコントロールすることが大事!
疲労がたまったままでは、トレーニング効果が見えづらい
しっかり休むこと=甘えではなく、トレーニングの一環




コメント